
藤本国彦さんプロデュースによるビートルズを語るトーク・イベント「ビートルズの世界 AROUND THE BEATLES 2022」が4月22日LOFT9 Shibuyaに於いて開催された。第3回のゲストは元『ミュージック・ライフ』誌編集長 星加ルミ子さん。日本で最初にビートルズを取材した編集者としてお馴染みの星加さんならではのエピソードに加え、本邦初公開となる写真も交えての2時間の熱いトークが交わされた。
記者としてのモットーは<取材する相手との距離感を大切にする>こと。
でも、ビートルズには時として距離感を忘れました(笑)

1965年ビートルズ初取材時の星加ルミ子さん
藤本国彦(以下藤本):「ビートルズの世界 AROUND THE BEATLES」今回のゲストは星加ルミ子さん。小野洋子さんと並んでビートルズに一番多く会った日本人(笑)。配信のゲストは初めて。ご紹介します星加ルミ子さんです。(場内拍手)
星加ルミ子(以下星加):二人ともビートルズ・フリークですからよくお会いしてたんですけど、今日は久しぶりですね。
藤本:星加さんは65年の初取材以降69年まで毎年ビートルズに会われてますが、今日は本邦初公開となる1968年末アップル・オフィスでの写真なども含め取材時の写真を見ながらお話を伺います。星加さんが『ミュージック・ライフ』の編集部に入られたのは1961年4月。
星加:その前、半年間はアルバイトとして写真や原稿の整理をしていました。
アルバイトから半年後に正式入社。ビートルズの情報が入ってくるのはそれから2年後の1963年。東芝音楽工業のディレクター高嶋弘之さん(ヴァイオリニスト高嶋ちさ子さんの父)が持ち込んだアセテートのテスト盤(「抱きしめたい」「プリーズ・プリーズ・ミー」)が最初の出会い。最初はイギリスでの爆発的人気の実感がなかったものの、アメリカの音楽専門誌に広告が派手に出始めたのを期にビートルズに注目。数少ないアーティスト写真を元に『ミュージック・ライフ』1964年4月号の表紙を飾ることとなる。その号は書店店頭で表紙だけが破り取られるなど大反響を呼び、さらに中高の女学生が編集部を訪れ新しい情報や写真を求める声が急増。通信社からの写真だけや記事だけでは対処できなくなる大ブームに。
 星加:64年にビートルズはアメリカでライヴを行い、人気番組『エド・サリヴァン・ショー』に出演と世界的なスターになって行く。それまでなんとか情報をかき集めて記事を作っていたものの、いよいよネタが尽きてくるんです。なんともならない──となったとき、当時の『ミュージック・ライフ』編集長草野さん(会社創業者の長男、作詞家漣 健児)が無理難題を言う人で(笑)、突然、“じゃあ星加さんロンドンへ行って会っておいでよ”と言うんです。
星加:64年にビートルズはアメリカでライヴを行い、人気番組『エド・サリヴァン・ショー』に出演と世界的なスターになって行く。それまでなんとか情報をかき集めて記事を作っていたものの、いよいよネタが尽きてくるんです。なんともならない──となったとき、当時の『ミュージック・ライフ』編集長草野さん(会社創業者の長男、作詞家漣 健児)が無理難題を言う人で(笑)、突然、“じゃあ星加さんロンドンへ行って会っておいでよ”と言うんです。
60年前、ようやく海外渡航が自由化された頃の渡英取材は大変なことだらけ、高額な飛行機代、海外持ち出し外貨の制限、そしてそれ以上にビートルズ取材の当ても皆目見当がつかない状況だった。64年終わり頃からの準備、まずイギリスの音楽出版社に<ビートルズに会いたいのだがどうすればよいか?>と片っ端から手紙を書き伝手を頼った。マネージャー、ブライアン・エプスタインからはすでに丁寧な取材お断りの連絡があったが、なんとかする術はないのかと懐柔のお土産などを画策。
星加:海外では日本のカメラとかオートバイに注目が集まっていた頃──、そこで絶対にNOと言わせない物を考えに考え抜いて「刀」を思いついたんです。イギリスは女王陛下と騎士の国ですから刀剣は身近な存在、さらにヴェネツィア国際映画祭で受賞した黒澤明監督の「七人の侍」などもあり、「刀」を持っていくことに決めました。それも本物を。スーツケースに入らないので、今ではあり得ないことですけれど、模造刀四振りと一緒に紙袋に入れて機内持ち込みで(笑)。会えるかどうかも全く白紙でしたけど着物一式も持って行きました。
ロンドンに入る前には万一ビートルズに会えなかった時のために──とハンブルクに降りて彼らが出演していた「トップ・テン・クラブ」や「スター・クラブ」を取材。その後一週間パリに行って、フィリップス・レコードの手配で当時流行っていたフレンチ・ポップスのフランス・ギャル(「夢見るシャンソン人形」等)や、シルヴィ・バルタン(「アイドルを探せ」等)らの取材をしてクロード・フランソワ(「マイ・ウェイ」共作者)は、彼のラジオ番組にゲスト出演もしました。“ボンジュール”“オヴォワー”って言っただけですけど(笑)。
それから当時パリに住んでいらしたカメラマンの長谷部宏さん、ニューヨークから来てくれた通訳担当のジョー宮埼さんとも落ち合って、いよいよロンドンに入ります。着いてすぐにエプスタインに会って、「刀」を渡したんです。その時彼の目がギラッと光ったので、これは95%くらい取材の可能性が出てきたな…と思いました。当然エプスタインは黒澤明監督のことも知ってましたし、刀をすぐに事務所の壁に掛けて目を見開いて見ていたので、これは98%OKかなと(笑)。
ところがそれから三週間音沙汰なし。当時携帯電話なんてありませんから、ジョー宮埼さんに何かあればホテルに伝言を残してもらうように頼んで、その間リヴァプール・サウンドと呼ばれていた一連のバンドはほとんど取材していました。それである日の午後ジョーさんからの「ルミ!来たよ! 5時にホテルに迎えが来るから準備して!」という伝言メモを見て、以降の取材は全部キャンセル、部屋で着物に着替え、資料やお土産を持って準備しました。
一階のミキシング・ルームではジョージ・マーティンを始め、音楽出版社のディック・ジェイムス、EMI海外宣伝部長のスタンさんとかと会い、そこからはもう夢見心地で地下にあるEMIスタジオでビートルズのメンバーと会いました。
 藤本:メンバーそれぞれに会った最初の印象はどうでした?
藤本:メンバーそれぞれに会った最初の印象はどうでした?
星加:階段を降りたら、一番最初に目を輝かせて飛んで来たのがジョージ・ハリスン。着物に興味を持ったようで、帯や袖に触りながら、“なぜこのベルトはこんなに太いの?” “このスリーヴが長いのはなぜ?”とか質問攻め。ジョン・レノンは離れたところで、見てるような見てないような顔をしてしゃがみ込んでいました。“あ、この人苦手かも…”と思ったんですけど、後に一番仲良くなって。誕生日も近いんです。私が9月10日、ジョンが10月9日。後に“君は一ヶ月俺のエルダー・シスターだ”って言われました。
藤本:ジョンは人見知り?
星加:だんだん分かってきたんですけど、ジョンっていうのは本当に警戒心が強いというか、人見知りなんですね。初めての人や物には最初警戒して、大丈夫だと思ったら近づいていく。彼は一番男っぽく、俺に着いてこい!って風に見えるんですけど、見かけによらず一番繊細でびっくりしました。いつも一番最後に輪に加わってくる、でも加わったら最後、ポールに叱られるくらいのもの凄いブラック・ジョークを言ってたみたいです、私なんかほとんど理解できなかったけど。
藤本:ポールの印象は?
星加:ポールは全部仕切ってくれました。よく喋る楽しい人で。『ミュージック・ライフ』読者からの質問状も、“君の英語じゃ明日の朝までかかっちゃうから、アンケート用紙を貸して”と言って、“これに答えて”とメンバーにそれぞれに配ってくれました。みんなあちこちに座って一生懸命書いてくれて、四人とも純真でスレっ枯らしたところが一つもない人たちでした。一歩外に出ればファンからもみくちゃにされるスーパースターでしたけど。
藤本:人気絶頂の65年に星加さんが会っているというのが本当に凄いんですけど──、リンゴはどうでした。
星加:リンゴはおとなしいです、だいたい後手を組みながらニコニコして見守ってる。なんでも一番最後に自分の方から言ってくる。やっぱり最後にメンバーになったからか、大人というか分をわきまえて一歩下がって、自分が自分がって出て来ることは全くない人ですね。
 藤本:日本公演は何回かご覧になりました?
藤本:日本公演は何回かご覧になりました?
星加:最初の日は記者招待で、最後の日はひょんなことからプロモーターの永島達司さんと。永島さんが “ルミちゃん、俺。皆んなから吊るし上げをくらって大変なんだよ。<なぜミュージック・ライフの星加ルミ子だけ、ビートルズに合わせたんだ!?>”って、他の週刊誌とかから責められて。“彼女はメンバーに直に会ってるし、直接エプスタインと交渉して会ってるんだから──”と言っても納得してくれなかったそうなんです。その日は最終公演の日で、これから観に行くという永島さんにお願いして、武道館の客席からは見えない所に設けられたスポンサー招待席に座らせていただいて、ジョン・レノンがサングラスをしたステージを観ることができました。
来日時のホテル取材では、有名なジョン・レノンの「シェー」ポーズも撮影された。“日本のキッズたちの間では何が流行ってるの?”というジョンの質問に、とっさに思いついた漫画「おそ松くん」のギャグを実演したところ、それをジョンが真似てくれたもの。後に作者の赤塚不二雄先生からも感謝された。約1時間くらいの滞在中、ジョンは部屋に東芝音工が持ち込んだステレオッセットで日本の民謡をかけて、えんやーとっと〜♫と唄われる「斎太郎節」を熱心に聴いていた。後に「アイ・アム・ザ・ウォルラス」のエンディングに聞こえる「エンヤートット」はここからのアイデアではないか…?というのが星加さんの推察。
藤本:66年8月の全米ツアーのお話を伺いたいのですが。
星加:ビートルズが日本から帰る寸前にブライアン・エプスタインから “8月の公演、一緒に来るかい?“と思いがけない取材の誘いがあり、帰国後すぐに、プレス・パス<公演中のビートルズと一緒に行動できてどこでも自由に取材できる>というこの上もない物が送られてきました。エプスタインのお墨付きをいただいた取材陣は、アメリカ、イギリス、フランスなどのショービジネス関係の記者が5人、カメラマン5人計10人。私は14公演のうち大都市5カ所(シカゴ、メンフィス、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ)を取材しました。
シカゴのインターナショナル・アンフィットシアターではフロアに散らばったメンバーへの取材。当時キリスト教発言問題でジョン・レノンに取材が集中し、次にポールに記者が集まる中、リンゴ・スターを取材しようとしたら、逆にリンゴが “今、ポールのところが空いてるから先にポールのところに行った方がいいよ──”と教えてくれた。
ニューヨークのシェイ・スタジアムでは何百人というグラウンド警備の人数や、4階~5階まである巨大な観客スタンドからセーフティ・ネットに落ちてくる女の子たちに驚かされ、終演後は装甲車のような車でスタジアムを後にするメンバーを見送った。
サンフランシスコのキャンドルスティック・パークでの最終公演の後、ロサンゼルスのバンガローのプールで開かれたアフター・パーティにも参加。エリック・クラプトンもいて彼がギターで弾く「サンフランシスコ・ベイ・ブルース」に合わせてジョージ・ハリスンが歌うシーンにも遭遇、そのまま大合唱になり宴は深夜12時近くにお開き。その場にはアルコールはあってもドラッグ等は一切ない、品行方正な四人に感心した。
 星加:当時はこれが最後のコンサートになるとはメンバーも思ってなかったんじゃないですか。ブライアン・エプスタインはまだ存命で、コンサートのブッキングはプロモーターと彼の間で決められてましたから。エプスタインが67年8月に亡くなってからですね、コンサートをやらなくなったのは。ジョン・レノンも“コンサート・ツアーはもう嫌だ、ビートルズはもう解散だ”って来日した時リンゴと一緒にホテルで叫んでましたから。
星加:当時はこれが最後のコンサートになるとはメンバーも思ってなかったんじゃないですか。ブライアン・エプスタインはまだ存命で、コンサートのブッキングはプロモーターと彼の間で決められてましたから。エプスタインが67年8月に亡くなってからですね、コンサートをやらなくなったのは。ジョン・レノンも“コンサート・ツアーはもう嫌だ、ビートルズはもう解散だ”って来日した時リンゴと一緒にホテルで叫んでましたから。
藤本:星加さんはエプスタインが亡くなった一ヶ月後、再度ロンドンEMIスタジオに行き、そこで「フール・オン・ザ・ヒル」の曲が生まれていく現場に立ち会うことになるんですね。
星加:最初ポールがくしゃくしゃのメモ紙を持ってきて、それを見ながらピアノで弾き始めたんです。そんな最中なのに長谷部さんにはどんどん写真を撮ってもらって(笑)。そこにジョンが入ってその紙を取って、歌詞に手をいれたのか何か書いた。ポールはピアノを弾きながらメロディを歌ってそうやって二人で作っていると、いつの間にかジョージとリンゴが現れて皆でピアノを囲んで。一通りやり終えると間奏部分に何か楽器を入れたいとポールがジョンに言ったんです。色々アイデアを出してからどちらともなく“ここはリコーダーがいい”となりました。そしてスタジオに置いてあった10本くらいの中からポールが選んで、「フール・オン・ザ・ヒル」のあのメロディを吹いた。ジョンも“それがいい”ってあっという間に決まったんです。リンゴはスタジオの隅のドラム・セットに座り、ジョージはギターを持って、ジョンもギターで、4人でなんとなく「フール・オン・ザ・ヒル」をやり始めました。そんな、まさに曲が生まれる始めに私は居合わせたんだ──と後で気がついてびっくりしました。普通そんな場に記者を呼ばないだろうし、私もそれを知っていたら遠慮してました。
藤本:それだけ『ミュージック・ライフ』という媒体と星加さんが信頼されていたんだと思います。その時の長谷部さんの写真には小野洋子さんも写っていた。
星加:スタジオの隅に白い服を着てうずくまっている髪の長い人がいたんです。
藤本:スタジオの模様は『ミュージック・ライフ』67年11月号に掲載されています。星加さんはこの時もビートルズ以外にジェフ・ベック、ジミ・ヘンドリックス、ピンク・フロイド、トラフィック、トロッグスといった錚々たる人たちに会っていて、取材のエピソードもたくさんあります。
星加:65年の最初のロンドンでも、リヴァプール・サウンドと呼ばれた有名なグループ、例えばデイヴ・クラーク・ファイヴやハーマンズ・ハーミッツとか片っ端から取材しましたからね。そういったビートルズ以外の話をできる機会を。
藤本:是非やりましょう!
その後も星加さんとビートルズの不思議な縁は続く。68年、映画「マジカル・ミステリー・ツアー」の日本上映交渉という大役を任された時は、ロンドンに二度も足を運んだが交渉は難航。ところが偶然会ったポール・マッカートニーによる仲立ちの電話一本で難題は無事解消。映画のテレビ放映、武道館上映が実現した。
同年12月23日にはアップル・コアの社屋(映画「ザ・ビートルズ:GET BACK」でもお馴染み)の社員クリスマス・パーティにも偶然参加、リンゴの息子(ザック&ジェイソン)の面倒を見、サンタクロースに扮しプレゼントを配ってお疲れモードのジョン&ヨーコにインタビューも行い、「悲しき天使」が大ヒットしていたメリー・ホプキンをジョンに紹介された。この時訪れたアップルのオフィスに座る星加さんの写真がつい数日前発掘され、本邦初公開ということでスクリーンに映され藤本さんが壁の掲示物を解説。

文中にある本邦初公開写真 アップル・オフィスの星加ルミ子さん
そして翌月69年1月30日アップル・コアに、誰かメンバーが居るかなぁと出かけたところ屋上から爆音が聞こえて街中が騒然とする光景に出くわす。静かになってからビルに入ると、演奏を終え屋上から寒さに鼻の頭を真っ赤にして降りて来たビートルズに遭遇。ポールは “Hi! Rumi! Are you in London?”といつもの挨拶の言葉をかけてきた。
藤本:駆け足になってしまいましたが、63年から69年の星加さんとビートルズのお話を伺ってきました。最後に、実際にビートルズに会って一番多く身近で取材された星加さんですが、改めて2022年の今から見て、ビートルズに対してはどんな思いでいらっしゃいますか?
星加:ミュージック・ライフという音楽雑誌の記者をしていたおかげで、ビートルズを取材することができて素顔の彼らに何度も会っているわけですね。音楽の素晴らしさは皆さんもご存知の通りなんですが、私は実際に会ったときの四人の魅力──、色々な人やグループを取材しましたけど、こんな四人組には会ったことがないですね。当時本当の世界のスーパースターだった四人が、間近で会って話している時には、本当に普通のなんの気取りも衒いもない明るく清潔な青年たちでした。私は記者をやってきましたけど、取材する時のモットーがあってずっとそれを守ってきました。それは、<取材する相手との距離感を大切にする>ということ。相手がいくら馴れ馴れしくしてくれても距離感を縮めてはいけない、私はあくまでも取材する人で相手はされる人という距離感だけは絶対に守ろうと、これだけは頑なに守ってきました。ビートルズに関しては私が歳が近いということもあったし、同じような感覚で昔聴いた曲の話とかをしたせいかもしれませんが、世界のスーパースターでありながら本当に親しみやすい素直な青年たちであったことに驚きました。今、改めて驚いていますけれど、いつ会っても何度会っても何の気取りもなくいつも同じに接してくれた。彼らは優れたミュージシャンであったと同時に、優れた四人の人間でもあったとつくづく思います。長い間記者をやってきましたけど、これほど気持ちよく取材できて後味のよかった人たちはいない、これは褒めすぎでもなんでもないんです、いまだにそう思っています。
藤本:星加さんの距離感がよかったんですね。
星加:でも、ビートルズは時として距離感を忘れました(笑)。特にリンゴ・スターなんか朝食をサーブしてくれて一緒に食べた仲ですから(笑)。
藤本:子供たちの面倒も見させて。
星加:それでも、あくまで自分はこちら側、相手はあちら側というある程度の距離感は絶対に守ろうとしました。だからあんなに長く、毎年解散するまでビートルズを取材できたのかな──と思っています。最後はちょっと自慢になりました、すみません(笑)。
藤本:いや、もう星加さんは生きる伝説と言われてますから。
星加:シーラカンスじゃない(笑)。
藤本:では、また機会を作って星加さんとご一緒できればと思います。
星加:ビートルズ以外に私が会った有名人、例えばミック・ジャガーとかいっぱいいますから、そういう人たちの素顔とかをする機会とかも。
藤本:そうですね、是非。今日は星加ルミ子さんをお迎えしてお送りしました、ありがとうございました。
星加:皆さんありがとうございました。
会場大拍手
この後サイン会が行われた。
◎当日の模様はアーカイヴ配信中です
5月6日(金)23:59まで視聴可能です。(その間も下記にて配信チケットがご購入頂けます)
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9/211873
星加ルミ子 関連書籍
-
購入する

-
私が会ったビートルズとロック・スター
四六判 / 200ページ / ¥ 1,540
元『ミュージック・ライフ』編集長の星加ルミ子による書き下ろし音楽エッセー本。
1965年6月15日、ロンドンEMIスタジオでのビートルズ単独会見から始まる、自身の音楽人生を振り返った書き下ろしエンタメ・エッセー。ビートルズやエルヴィス・プレスリーといったスーパースターを支えた人々にスポットを当てつつ、60年代の日本、世界、音楽、社会、文化を俯瞰する。【CONTENTS】
第1章 ビートルズとブライアン・エプスタイン
スーパースターとその時代背景
マネージャーとひと口にいうけれど……
エルヴィスとパーカー大佐
“タレント”と“アーティスト”
パーカー大佐とご対面
素顔のブライアン・エプスタイン
ブライアン・エプスタインとロバート・スティグウッドの確執
アンディ・グレイとマイケル・ロジャーズ
ブライアン・エプスタインとはじめての対面
ブライアン・エプスタインへの献上品
エプスタインのタレント・スカウト能力
『プレイボーイ』誌と社長のヒュー・ヘフナー
知らない、無知ということは、時として人を大胆にする
ビートルズを注視するきっかけを作ってくれた「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」
ロック・ミュージックの変容
ウォーカー・ブラザーズ
『ミュージック・ライフ』編集部
“使い上手な人”と“使われ上手な人”
第2章 1960年代という時代に
60年代の若者達
若者達の代弁者。ボブ・ディランの登場
ビートルズとMBE勲章
星加ルミ子のビートルズ音楽講座
ビートルズの音楽センスは、どのようにしてつくられたのか
サミー・デイビスJr.とダニー・ケイ
5人目のビートル、ジョージ・マーティン
海外の音楽出版社との楽曲の契約
みナみカズみ/安井かずみ
カーナビーツと「オーケイ!」
音楽著作権バイヤーとしての手痛い出来事
伝説の音楽番組『ビート・ポップス』
訳詞を手がける
第3章 私の愛聴盤
私の愛聴盤
ポール・サイモン
ロッド・スチュワート
エリック・クラプトン
私が胸をときめかせたミュージシャン、ベスト3
そしてビートルズ
デイヴ・マシューズ・バンド
おまけの章
エピソード 1
エピソード 2
エピソード 3
エピソード 4エピソード ランダム
モダン・ジャズ・アレルギー
ロン・ウッド
ドノヴァン
ピーター&ゴードン
マリアンヌ・フェイスフル
ミック・ジャガー
ビートルズ 関連書籍のご案内
-

MUSIC LIFE 1960年代のビートルズ〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2020/07/09発売
¥ 1,650
-

MUSIC LIFE 1970年代ビートルズ物語〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2017/03/29発売
¥ 1,540
-

MUSIC LIFE 1990年代のビートルズ〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2019/07/08発売
¥ 1,540
-

MUSIC LIFE ザ・ビートルズ 1980年代の蘇生〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2018/07/09発売
¥ 1,540
-

MUSIC LIFE ザ・ビートルズ ゲット・バック・プロジェクトの全貌〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2022/02/17発売
¥ 1,870
-
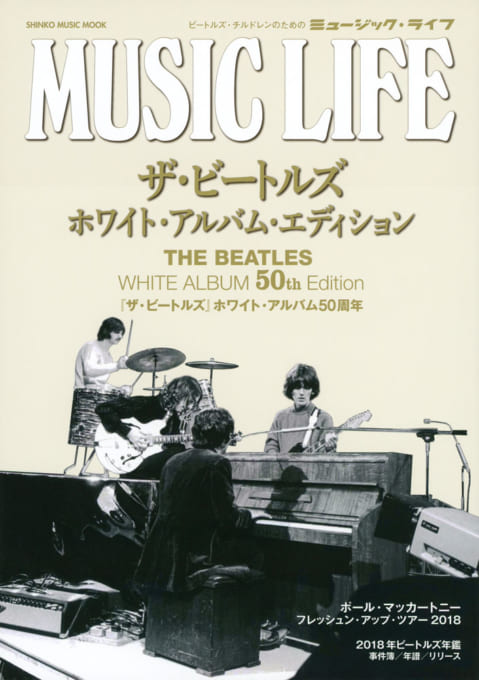
MUSIC LIFE ザ・ビートルズ ホワイト・アルバム・エディション〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2019/02/18発売
¥ 1,540
-

MUSIC LIFE ザ・ビートルズ日本公演 1966 特別版〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2018/06/18発売
¥ 1,980
-

MUSIC LIFE ザ・ビートルズ来日前夜〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2016/2/8発売
¥ 1,540
-
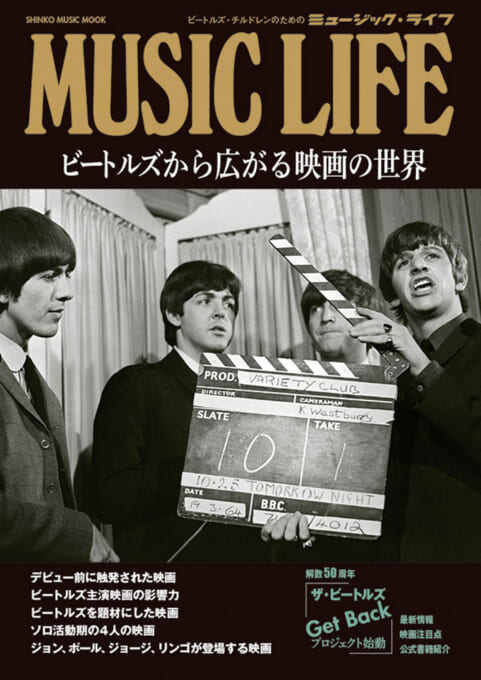
MUSIC LIFE ビートルズから広がる映画の世界〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2021/09/27発売
¥ 1,870
-

MUSIC LIFE ビートルズの音楽遺産 2014-2015〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2015/1/26発売
¥ 1,540
-

MUSIC LIFE ビートルズ主演映画〈シンコー・ミュージック・ムック〉
2019/10/08発売
¥ 1,540
-

ミュージック・ライフが見た“元”ビートルズ
2011/11/30発売
¥ 3,143
-

ミュージック・ライフが見たビートルズ
2010/10/18発売
¥ 2,619
![シンコーミュージック・エンタテイメント | 楽譜[スコア]・音楽書籍・雑誌の出版社](https://www.shinko-music.co.jp/wp-content/themes/shinkomusic/images/logo@2x.png)